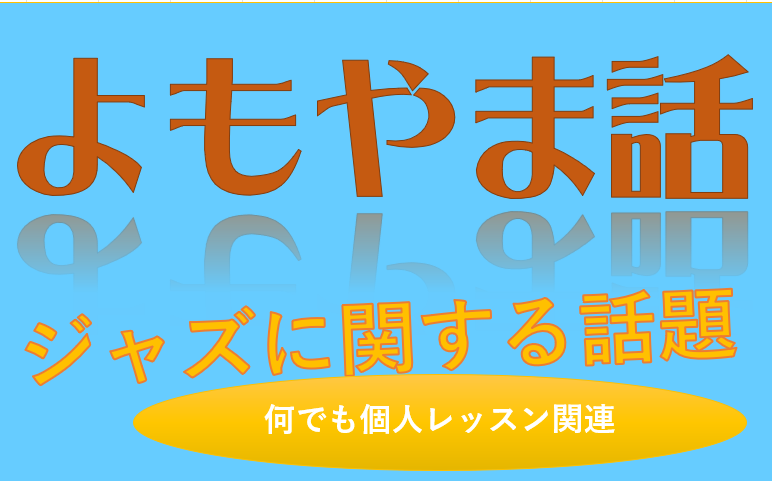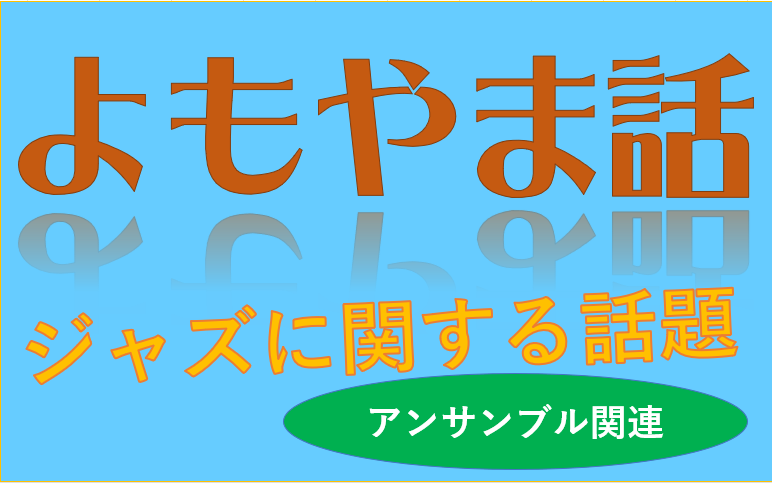
よもやま話として、基本的に思いつきの文章を乗せてみようという話の1発目です。
今回の話題は「テンポキープ」について。
◆「テンポキープ」って当たり前のことだけど難しい
演奏が始まった時はゆったりしたスイングで始まったのに最後のテーマに成ったら随分早く成ってて、バップ系の曲なんかだと最後のテーマが弾けなくてボロボロに成って恥ずかしい思いをするってケースに遭遇してしまう事も多いんじゃないでしょうか?
よく「演奏が走る」と言う表現が有ります。
前述のように、別に早くしようと思ってないのに、テンポが速くなっていくことですね。
さて、この逆のパターンも有ります。
いわゆる「もたる」ってやつで、知らないうちにテンポが遅くなるという現象です。
チェロキーをテンポ320で始めたつもりが、気が付いたら280くらいまで落ちてしまって、疾走感が消えてしまうパターンですね。
さて、ここでテンポキープに関して私が知ってるインパクトの強い格言をお教えしましょう。
「下手は全部ミディアム」
さて、これは何を意味するかと言うと、下手な人が演奏すると、遅い曲は早くなって、速い曲は遅くなって、結局自分がやりやすいミディアムテンポに近づいて行くという意味です。
自分がやりやすいテンポは一つでは無くて、120~240とかの一定の範囲に成ると思いますが、この範囲に入るまで、どんどんスピードが変化してしまうという事です。
何故なのかと言うと、一言「下手だから」と言う意味なので、結構インパクト強いでしょう?
逆から言えば、意識的にテンポをキープするトレーニングをしてないと走ったりもたったりするのが当たり前という事ですね。
それだけ、難しいという事です。
人間は、興奮すると心臓の鼓動が早くなります。
だから、これにつられてテンポが速くなるという話も有ります。
それだけ難しいんだけど、ちゃんとキープする為に、しっかりトレーニングする必要があるという事ですね。
◆ メトロノーム使って練習しても本番では走る
勿論、メトロノームを使用して正確なテンポをキープするトレーニングをするという事は重要です。
しかし、メトロノームに合わせに行った結果正しいテンポで演奏できるようになったという状況では、実際に生身の人間と演奏した時に、走ったりもたったりすることを回避する事は出来ないと思います。
じゃあ、どうすれば?
メトロノームに合わせに行ってる時点で、テンポ感はメトロノームに依存している訳で、実際の演奏の場合はメトロノームなんか当然ないので、依存する先が無くなります。
その結果、共演者のテンポに依存したりするわけですが、共演者が常に正確なテンポで演奏してくれるわけでは無いので、お互いが悪い影響を与え合って、どんどんテンポが不安定に変化するという事態を招きます。
この状態が、走ったりもたったりしている状況だと思います。
◆ テンポをキープするためのテンポに対する考え方
テンポをキープする事は大変難しい事です。
でも、これをおろそかにすると良い演奏は出来ないでしょう。
では、テンポをキープする為には、何をすればよいかについて私なりの考えはこうです。
演奏して居る時に、共演者のテンポに依存するのではなく、自分がしっかりテンポ感を出して、共演者との微妙なずれを把握しながら、演奏をすることがスタートラインです。
また、共演者のテンポも当然ぶれるのが前提なので、ぶれた時に共演者にかすかに伝わるように、少し後ろに、少し前にビートのポイントをずらして、「あなた走ってますよ」「あなた遅くなってますよ」を気づかせてあげる必要が有ります。
逆に、共演者のテンポ感に常にアンテナを立てておいて、自分のテンポより少し後ろに来てるときは、自分のテンポが走ってるんじゃないかとか、セルフチェックしながら演奏する事を意識していれば、共演者間で正しいテンポ感を共有し補正しながら演奏を継続することが出来るように成ります。
つまり、誰かに依存するわけでは無く、自分でリズムを出して、出したリズムと共演者が出したリズムが合っているかどうかを常にチェックして、ずれた場合は補正したり、共演者に音でメッセージを送ったりして、バンドのテンポ感を守る必要が有ります。
テンポを合わせに行った結果正しいテンポで演奏できるではなく、自分が出しているテンポがメンバーが出したテンポと結果的に合っている状態が本来正しい状態だと思います。
◆ ドラムにテンポキープして貰うという間違った考え方
共演者の中にドラムと言うパートが有ります。
ドラムが正確なテンポで演奏する結果、バンドのリズム感やテンポが安定すると考えている人って結構多いと思います。
ドラムは、基本的にリズムを司るパートな訳ですから正確なテンポを出すのは当たり前だろうと思うかもしれませんが、ことテンポキープに関して言えば、ドラムが一番難易度が高いように思います。
理由は、演奏中に動かす関節の数が圧倒的に多いからです。
ドラムの場合は、常に両手両足を動かします。
稼働部所が多ければ、誤動作する確率も当然上がります。
だから、ドラムがテンポキープするのは、他の楽器がテンポキープするより本来は難易度が高いのです。
テンポキープは、ドラム任せでは無くて演奏者全員が意識しなければ成立しません。
◆ テンポが変化してしまう原因
テンポが変化してしまう原因として、単純に基礎練習が不足していると言ってしまえばそれまでですが、どんなメロディーを演奏するかと言う事もかなり影響してくると思います。
ミディアムテンポの曲ばっかり演奏してる人のフレーズの引き出しにはミディアムテンポで演奏するときに適したフレーズがたくさん並んでる事でしょう。
その結果、遅いテンポの時も、速いテンポの時も、慣れ親しんだミディアムテンポの時に使うフレーズが出てきて、結果的にミディアムテンポに引っ張られる事に成ります。
普段から、いろんなテンポで演奏する練習を行っていれば、こんな事には成らないでしょう。
◆ 楽器によってビートのタイミングが変わるという迷信
例えば、ベースの場合は音の立ち上がりが遅いので少し前に突っ込んだタイミングで弾くとか言われるケースが有ります。
しかし、こう言うのはジャストが完ぺきに取れるように成ってから考えればいい事であって、自分がキープできない言い訳に、こういう事を使うのは間違いだと思います。
まずは、ジャストのタイミングを意識する必要が有ります。
レイドバック等に関しても同じことですね。
◆ メロディー楽器のビートに対する考えかた
メロディーに関しては、タイムをキチキチ演奏するより、語るようにおおらかに捕えて演奏する方が、感情が乗った良い演奏が出来ると思います。
この場合、周りのパートが出す正確なビートとはずれる事に成りますが、だからと言って正確なテンポ感を意識する必要が無いかと言えば、そんなことは有りません。
実際に出ている音と、腹で感じているテンポ感は当然違いますが、腹で感じているテンポはバンドの他のメンバーと一致している必要が有ります。
◆ で、まとめると
・リズムキープはとても難しい
・意識して取り組まないと出来ない
・共演者とのタイム間の相対的なずれを常に意識する必要がある
・ドラムに頼るのは大間違いで、自分自身がテンポを出さなきゃいけない
・いろんなテンポで練習する
・テンポにマッチしたフレーズを使う
という、所でしょうか?
テンポキープって難しいからこそ、意識して練習しなきゃダメって事ですね。
Views: 28