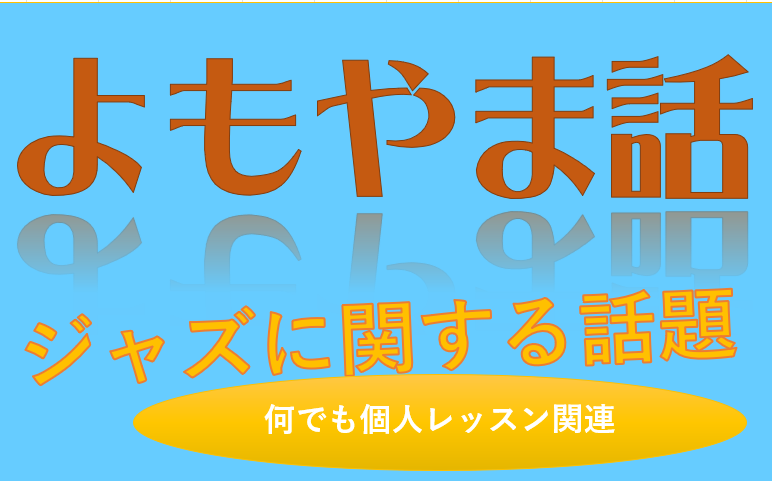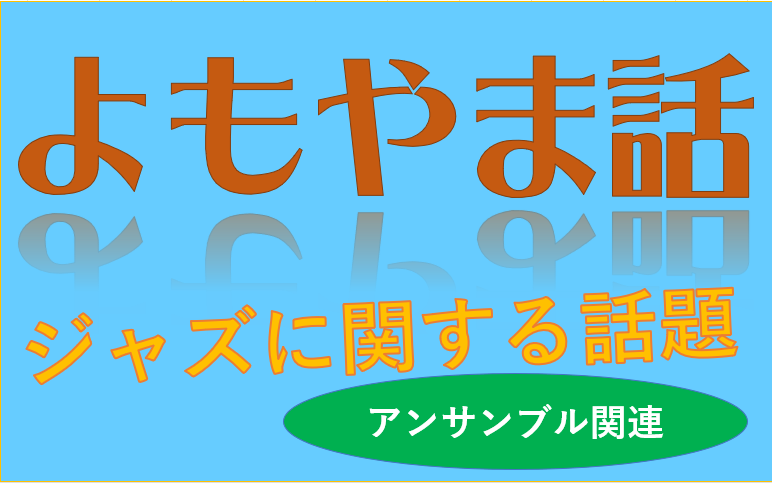
共演者がどんどん走って行ってテンポが早くなるんですが自分も付いて行った方が良いんでしょうかについて考える
以前、「テンポキープについて考える」で書いた話に関係する事です。
自分はキープしているつもりでも、共演者の中には自然にテンポが早くなっていく人が含まれている時に、自分はどうしたら良いかという事について少し考えてみたいと思います。
テンポが早くなっていく人が居る場合、早くなったテンポに合わせて演奏する方が「自然」だと思うという意見が有ります。
テンポが走る状況になる場合の原因は概ね下記の二つでしょう。
1.そもそもスキル不足でテンポキープ出来なくて走ってしまう。
2.音楽的な表現の一環として「意図的に」テンポアップやテンポダウンを狙っている。
2のケースは無しでは無いと思いますが、やるなら最低限ちゃんとキープは出来るけどと言うのが前提に成ると思います。
それが、「意図的に」という部分ですね。
殆どのケースは1だと思います。
誰かが走ってしまったとき、無理矢理テンポキープすると共演者間でテンポにずれが生じておかしくなるので、「自然」にする為に自分も早くするのである。
これは単なる「言い訳」「正当化」「逃げ道」でしかないと思います。
結果として、最初のテーマと最後のテーマのテンポは大きく変わって曲のイメージも変わってしまいますし、前に書いたことと同じですが、エンドテーマのテンポが早すぎてテーマのメロディーが正確に弾けないという残念な現象に繋がってしまいます。
「自然」にする為に自分も「意図的に」テンポを上げて行くのではなく、自分もコントロールできていないので「つられて」テンポが早くなってしまう事に対する言い訳ですね。
言い換えるとテンポキープ失敗に関する「被害者」だったのが「加害者」に成ってしまった状況ですね。
では、テンポが132の曲を演奏している時に、誰かが135位の感覚で走り始めたとき、共演者が132のままだったら、どんどんずれて行って音楽が成立しなくなると考えるかもしれません。
しかし走ってしまう人は「意図的」では無いので、周りが付いてこなかったら、周りに「つられて」走らずにある程度同じテンポで留まります。
正確なテンポを自分から出しているわけでは無く、他の何かに依存している状況の場合に依存先が見えなくなって走ってしまうと言うのが殆どの走る現象の原因なので、周りが付いてこなかったら周りに依存する事で勝手に早くなっていくような状況では無くなります。
メトロノームに合わせて演奏するときは正確なテンポで演奏できるのにと言うのと似てますね。
メトロノームに「依存して」演奏するから走らないだけで、自分の中で正確なコントロールが出来ているわけでは無いから、溺れる者は藁をもつかむで、掴めるものが有ればそれに依存する訳です。
さて、今度は、走る側ではなくキープする側として考えてみましょう。
共演者が走る時、自分はどうしたら良いかですが132でテンポキープする事を前提として共演者のテンポが132より早くなっていったら・・・
知らん顔して132で演奏し続けると、当然演奏は崩壊します。
また、共演者に合わせてテンポを上げると、どんどん走ります。
では、どうするか
演奏するテンポが本来のテンポに戻るまで、共演者が演奏している走ったタイミングより少し遅いタイミングに音を出す事で、走っていく共演者にブレーキを掛け続けます。
この結果、共演者は少し後ろに引っ張られるような「もたった」感覚を持つため、走っていく自分のリズムに抑制が加わわっていきます。
但し、このような演奏をすることは、実際問題としてかなり辛い状況になります。
音楽的にというよりテンポキープする為に演奏しているような状態に成りますし、殆どのケースではブレーキを掛け続ける事にかなりのストレスを感じる状態に成ります。
この苦しさから抜けるために、自分も「被害者」から「加害者」側に回って走るテンポに依存して早くするのかもしれません。
「少し遅いタイミングで」と言うのが曲者で、現在のテンポや共演者の走り方によって、どの程度遅くするべきかは変わります。
これを、音楽的に壊れる事のないレベルで調整する事はかなり難しい事です。
しかし、このような訓練を行う事は、自身のテンポ感を向上させる、つまりテンポキープ力を高めるトレーニングとしてはとても効果があると思います。
共演者とのテンポのずれを常に意識しながら補正する作業を行う結果、テンポに対する感覚は研ぎ澄まされて行くのではないかと思います。
そう考えると、周りにいる走ってしまう人は、自分のテンポキープ力を向上させるトレーニングに協力してくれている人というありがたい存在と考える事も出来ますね。
Views: 40